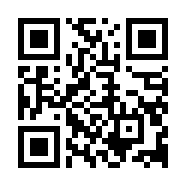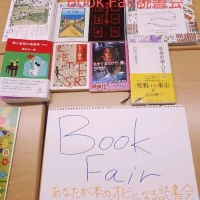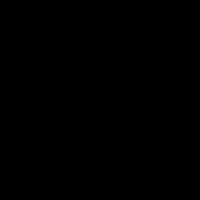『死ぬまで一生愛されてると思ってたよ』のアルバムの中では『イノチミジカシコイセヨオトメ』がすごい好きですね。自分のテーマみたいな。物語でいうと、『ちひろさん』っていう漫画が合いそう。街のお弁当屋さんで働いている元風俗嬢の美人な女性の話。ちひろさんというより、ちひろさんが居た世界にこういう女の子が居たような気がする。
ーカリスマ書店員・新井見枝香
ーカリスマ書店員・新井見枝香
0件のコメント

1962年に生きる青年と1882年に生きる乙女が、机の隠し抽斗を介して文通する。
静かな春の夜、80年の時に隔てられていても、同じようにペンを走らせている二人の姿には、ショパンの夜想曲第2番を添えたくなる。
静かな春の夜、80年の時に隔てられていても、同じようにペンを走らせている二人の姿には、ショパンの夜想曲第2番を添えたくなる。
0件のコメント

林太郎の背中を押す言葉の数々、RPGという冒険感がまさにこれ!という感じです。「きらめくような人生の中で君に会えて僕は本当に良かった」という歌詞、君を本に変えれば林太郎の気持ちそのものではないでしょうか?読みながら私たちも同じように思うことがあるのでは?
0件のコメント

物語のラストで、この楽曲である理由がわからはず。
0件のコメント

すれ違って、思い上がって、痛々しくて、生傷ばかりを抱え込んで生きる。
そんな僕らだからこそ、見えるものがある。
自分には才能があると、思い込んでいたあの日。
周りから相手にされていないと、勝手にふさぎ込んでいたあの日。
他人を自分の定規で勝手に図っていたあの日。
大切にしてた夢。目を背けていた淡い感情。
どうしようもなくこじらせていて、痛々しくて、笑われてしまいそうだ。
前はほんの少し嫌味を言われただけでも心が軋んで、動けなくなっていた。
一回り大きくなった今なら、ちゃんと前を向いて歩ける。
馬鹿にされてもへいちゃらだ。
いじらしい心に、長年心待ちにしていた春が訪れる。
「ほら、少しは生まれ変われたかい」。
そんな僕らだからこそ、見えるものがある。
自分には才能があると、思い込んでいたあの日。
周りから相手にされていないと、勝手にふさぎ込んでいたあの日。
他人を自分の定規で勝手に図っていたあの日。
大切にしてた夢。目を背けていた淡い感情。
どうしようもなくこじらせていて、痛々しくて、笑われてしまいそうだ。
前はほんの少し嫌味を言われただけでも心が軋んで、動けなくなっていた。
一回り大きくなった今なら、ちゃんと前を向いて歩ける。
馬鹿にされてもへいちゃらだ。
いじらしい心に、長年心待ちにしていた春が訪れる。
「ほら、少しは生まれ変われたかい」。
0件のコメント

"With no combat gear and Wall Rose breached, the 104th scrambles to evacuate the villages in the Titans' path. On their way to the safety of Wall Sheena, they decide to spend the night in Utgart Castle. But their sanctuary becomes a slaughterhouse when they discover that, for some reason, these Titans attack at night!"--
衝撃的な展開でした。信じていた善悪がぼやけ、どうなるのか想像つかないです。このバンドがいいと思いました(*´∀`)
0件のコメント

僕たちには夢も現実もない。あるのはそれぞれの「体験」だけだ。だから僕たちの会話は噛み合わない。僕たちは永遠にひとつにはなれない。「でも、それこそ素晴らしいんだ」と思えるには、まだちょっと時間が必要か。
0件のコメント